今すぐできる!熱中症対策【水分の摂り方】
梅雨が明けた途端、厳しい暑さが続いていますね・・・
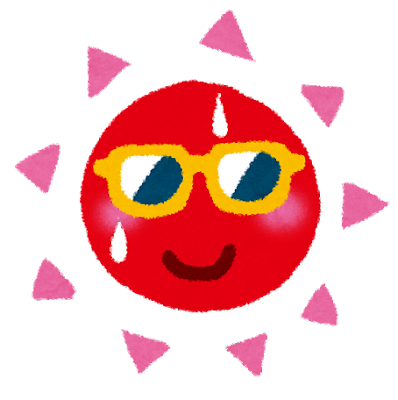
ここ数年は地球温暖化の影響か、私たちが子どもの頃とは比較できないほどの酷暑が例年続くようになってきました。(温暖化の話とかをし始めると、これはこれでめちゃくちゃ話が長くなるので今日はやめときます。笑)
今日は、まだまだあと2ヶ月は続くであろうこの暑さに負けないように、皆さんには元気でいてほしいので、私が最近勉強した「夏バテ対策」について、今日は水分の摂り方を共有したいと思います。
電解質
成人の体重の約60%は水分からなりますが、その体内の水分は単なる水ではなく、栄養や電解質や気体など様々なものが解けていて、それは「体液」と呼ばれます。体液には、電解質が含まれており、電解質とは、体液中に存在するミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、硫黄、鉄、亜鉛、セレンなど)のうち、水に溶けるとイオンになる物質(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リンなど7種)のことを言います。熱中症対策においては、この電解質を含んだドリンクを摂取することが非常に重要と言われています。
| 主要ミネラル | 生理作用 | 過剰摂取 | 不足 |
| ナトリウム Na | ・細胞外液の浸透圧の維持 | ・高血圧 ・むくみ ・動脈硬化などの生活習慣病 | ・疲れやすい ・食欲低下 |
| カリウム K | ・細胞液の浸透圧の調整 ・細胞内の酵素反応をサポート | ・高カリウム血症 | ・脱力感 ・食欲不振 |
| カルシウム Ca | ・歯や骨の形成 ・細胞の情報伝達 ・神経の興奮を抑える | ・泌尿器系結石 ・鉄・マグネシウム・亜鉛などの吸収阻害 | ・こどもの骨の発達障がい ・骨粗鬆症 |
| マグネシウム Mg | ・歯や骨の形成 ・酵素の正常な働きの促進 ・血液循環の促進 | ・軟便 ・下痢 | ・動悸 ・不整脈 ・神経過敏 ・抑うつ症 |
上の表の通り、カリウムは細胞の中にナトリウムは細胞の外に多くあります。この違いを利用して、神経や筋肉の細胞が刺激で興奮するようにできているため、均衡が崩れると、身体は大変なことになってしまうのです。
カリウムが細胞外に増えすぎると、少しの刺激で心筋が興奮して細かく震えてしまい、時には心停止することもあるようです。そのようなことが起きないように、普段は尿などで電解質濃度が調節されていますが、腎不全などの持病のある方などで、そうした機構が働きにくい場合は、カリウムの摂取を医師の指示等で制限されることがあり、主に、果物・生野菜・お刺身を制限されます。これは、先ほど書いたように、カリウムは細胞内に存在しているので、これらの生ものの生きた細胞を食べると自然とカリウムをとってしまうことになるのです。(ただし、熱を通せば大丈夫◎)
浸透圧
しょっぱいものを食べると、喉が渇いて水が飲みたくなるのはなぜでしょうか?考えたことはありますか?
水は、濃度の濃い方に移動する性質がある(浸透圧)ので、塩分(ナトリウム)を多くとると水が体内に引き込まれるのです。そうすると、血漿(血液中の体液のこと)の量が増え、結果的に血圧(血液が血管の壁を押す力)が上がります(血管がパンパンになるイメージ)。

このように、水はナトリウムについていきますが、なんと、ナトリウムは水についてくるわけではありません。下痢や嘔吐や暑さや運動など大量の汗で水と一緒にナトリウムも体から失われた場合、水だけをたくさん補給すると、薄まった体液のナトリウム濃度を元に戻すために体はさらに水分を尿として外に出し、逆に脱水が進んでしまいます。
そのため、脱水時はただの水ではなく電解質を含んだ水分を補給するのが良いのです。
アイソトニックとハイポトニック
では、電解質を含んだ水分というと、どんなものが望まれるでしょうか。
見出しに「アイソトニック」と「ハイポトニック」と書きました。いわゆる、スポーツドリンクや経口補水液のようなものを指しますが、その中にも違いがあり、その違いは浸透圧にあります。
| 安静時の体液比 | 塩分 | 糖分 | 吸収バランス | 摂取タイミング | |
| アイソトニック (等張液) ポカリスエット アクエリアスなど | 同じ濃度 同じ浸透圧 | 0.1~0.2% | 4~6% | 水分・塩分・糖分が バランスよく吸収 | 体液が薄くなると吸収速度低下 運動前後に飲むといい |
| ハイポトニック (低張液) アミノバイタル ヴァームなど | 低い | 0.1% | 2% | ↑より低いため エネルギーが必要な時は 糖分もあわせて摂る | 大量の発汗時 運動中や運動直後 |
学生のころ、運動部に入っていた方は運動中のスポーツドリンクを薄めて飲むように言われていた方も多いのではないかと思いますが、運動中はどちらかというとハイポトニックの方が適していたからということになりますね。

ちなみに、スポーツドリンクに含まれる糖分についても、細かく見ていくと「ブドウ糖」や「果糖」などの「単糖類(糖質の最小単位で、それ以上分解されずそのまま吸収されてしまう糖質のこと)」の割合が多すぎると、中性脂肪の増大、高脂血症、高血圧などにもつながりやすくなるため、多糖類に分類される、デンプン由来の糖質(マルトデキストリンなど)やグリコーゲン由来の糖質(牡蠣、エビ、ホタテなどに含まれていることが多い)、オリゴ糖などをチョイスするとさらに質が高まるのではないかなと。
| 大分類 | 種類 | 特徴 |
| 単糖類 | ブドウ糖(グルコース) | 人のエネルギー源 |
| 果糖(フルクトース) | 果物や蜂蜜の甘味 | |
| ガラクトース | 乳糖の成分 | |
| 二糖類 | ショ糖(砂糖) | ブドウ糖+果糖 |
| 乳糖(ラクトース) | ブドウ糖+ガラクトース | |
| 麦芽糖(マルトース) | ブドウ糖+ブドウ糖 | |
| 多糖類 | デンプン | 多数のブドウ糖で細かく構成 (分解されやすい) |
| グリコーゲン | 多数のブドウ糖で細かく構成 (分解されやすい) |
そして、水分補給としてコーヒーや緑茶などは適しているのか?という疑問もよく持たれるのですが、コーヒーや緑茶に含まれるカフェインには利尿作用があるため、大量に摂取すると尿と一緒に水分が排出されてしまうので、厳しい暑さで大量の水分補給が必要な場合には少し不向きかもしれません。(近年では、大量でなく適量であれば水分補給としての役割を持つと言われています)

あと、カフェインには交感神経を刺激してやる気を出したり、眠気覚ましの働きもあるため、リラックスして睡眠を迎えるための身体の準備として、夕方以降でその後の活動がない場合の水分摂取は純粋なお水が良いのではないかと思います。
夏時期のアロマトリートメント前後のポイント
まず、施術前、自覚がなくても脱水しているかもしれないので、しっかりノンカフェインのドリンクを飲んでいただき、体内の水分塩分濃度を調整していきます。歩いてサロンまでお越しいただいた方は尚更です。
猛暑の中歩いてこられたお客様については、まずは体温を下げてあげたいので、氷入りのドリンクとさせていただくことが多いですが、お車でこられたお客様は、ほんのりひんやりくらいの常温でお飲みいただきます。これは、冷たいドリンクによって、内臓が冷えて機能が働きにくくなるのを防ぐためです。
このとき、施術中にトイレに行くのが気が引けるから・・・という理由で飲まれない方もいらっしゃるのですが、長時間の施術になります。口腔内などの乾燥は免疫低下にもつながりますから、できる限り補給をお願いします^^(こちらでお出ししています)施術中にトイレに行きたくなったら、本当に本当に遠慮なく伝えてください。トイレに行ったら、また一口お水を飲んで再開しましょう^^
アロマトリートメントの施術は、精油による効果効能や、物理的にセラピストの手によって浮腫みを排出するように促していくので、施術後にもトイレに行きたくなったらしっかりトイレに行き、その後またしっかり水分摂取しましょう^^

では、今回はこのへんで♪
近々、また熱中症対策としてのタンパク質の摂取、ビタミンB群の摂取についても書いていこうと思います♪
最新記事 by Ayane (全て見る)
- アクティブレストとパッシブレスト【積極的休養と消極的休養】 - 2023年12月9日
- 心地良い睡眠を【外側編:換気、頭寒足熱、隙間にクッション】 - 2023年12月7日
- 手をケアした方が良い理由【ハンドケア、ハンドマッサージ、ハンドトリートメント】 - 2023年11月27日


